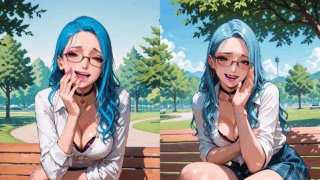朝起きると義理の母が‥

朝、布団の端を軽く揺らされて目を覚ますと、そこには再婚した父さんの若い妻――つまり僕にとっては義母が立っていた。彼女は笑顔で「おはよう」と言い、眩しい朝日よりもずっと可愛らしかった。眠気を引きずりつつも、僕の股間がむくむくと膨らむ。

この世界の理――僕は誰をイラマチオしても許される。ならば、目の前の彼女を試さない理由なんてない。手を伸ばし、あさっぱらから彼女の口内に押し込むと、「きゃっ」と小さな悲鳴をあげた。僕は満足げに微笑み、今日も最高の朝が始まるのだと確信した。
曲がり角で遅刻少女と‥

登校途中、角を曲がった瞬間、勢いよくぶつかってきたのは制服姿の女子高生だった。口には漫画のようにトーストをくわえ、目を丸くして「ご、ごめんなさい!」と慌てて頭を下げる。その姿があまりに教科書的で、思わず笑いをこらえきれなかった。だが次の瞬間、僕はもちろん‥

「ひゃあっ!」と甲高い声が弾け、パンが宙に舞った。周囲の通行人たちは見て見ぬふりをし、ただ日常の一コマのように受け入れている。僕は盛大に口内射精をした。
校門で睨みつける委員長

朝の校門前で、ひときわ冷ややかな視線を投げてきたのは――委員長だった。腕を組み、眉を吊り上げて仁王立ちしている。「校門前で騒ぎを起こす気?」と言わんばかりの眼差し。しかし僕は知っている。この世界のルールを。誰を相手にしても、僕のイラマチオは許されるのだ。

委員長の前に立ち、すっと手を伸ばし――顔を掴んだ。「ちょっ、ここで!?」その声に周囲の生徒たちは一斉に振り返り、ざわめきが広がる。僕は満足げに口の中にぶちまけ、朝日を背に校舎へと歩き出した。
横の席にはツンデレ幼馴染

教室に入ると、隣の席にはいつもの幼馴染が座っていた。長い髪を耳にかけ、ちらりとこちらを見て「な、なによ…」とツンとした声を放つ。彼女は典型的なツンデレで、僕に冷たくしながらも、誰よりも近くにいる存在だ。

授業が始まる前にすっきりさせたかった僕は、迷わず手を伸ばした。「ちょっ!や、やめっ…!」と顔を真っ赤にする。周囲のクラスメイトは、もうこの光景を見慣れているのか「またか」と小さく笑うだけ。
おとなしい国語の先生

一限目は国語。教壇に立つのは、物静かで美しい先生だった。黒板に流れるような字を書きながら、落ち着いた声で古文を読み上げる。その姿に、教室中の空気は凛と張り詰めていた。

僕は堂々と席を立ち、先生のもとへ歩み寄った。「……?」と振り返る先生の顔を掴み、ためらいなく口の中に挿入する。クラス中がどよめくが、誰一人として咎めはしない。むしろ「また始まった」と安堵したような空気さえ流れる。僕は口内射精で満足した。
授業参観での友達の母親

今日は授業参観の日。教室の後ろにはずらりと保護者たちが並び、いつもより空気が重い。生徒たちは妙に背筋を伸ばし、先生の声に普段以上に素直に従っている。そんな中、僕の視線は一点に釘づけになった。――高菜さんのお母さん。落ち着いた雰囲気と洗練された笑みをたたえた、美人だった。
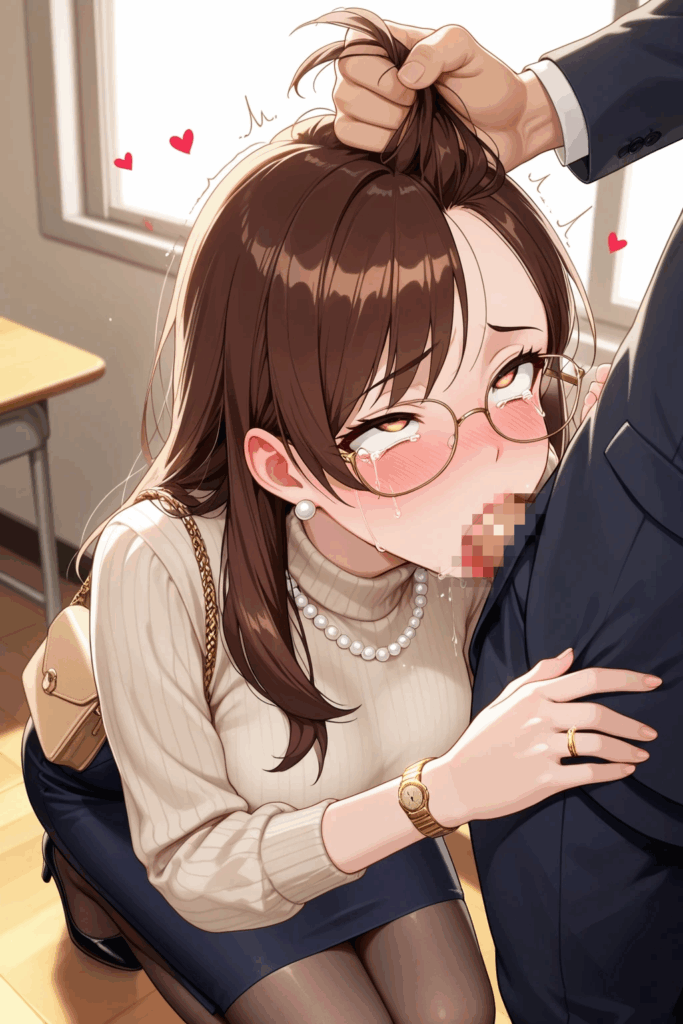
授業の最中、すっと立ち上がり、保護者席へ向かう僕を誰も止められない。そして彼女の前にペニスを差し出した瞬間、「あっ…!」と驚きの声とともに諦めた顔になった。生徒も保護者も呆気にとられたが、誰一人非難しない。僕は高菜さんの眼の前で母親を犯すと、満足げに席に戻る。静けさを取り戻した教室に国語の朗読が続いていった。
校舎裏には不良ギャル

昼休み、校舎裏へ足を運ぶと、そこには制服を着崩した不良ギャルが腰を下ろしていた。指先には火のついたタバコ。紫煙をくゆらせ、鋭い目つきでこちらをにらみつける。「見たな?」と低い声で言われても、僕は一歩も引かない。

おしおきの意味を込め、僕はためらいなく彼女の口にペニスをねじり込む。「なにすんのよ!」強がり混じりの声がはじけ、煙と一緒に威勢も消え去った。肩を震わせて泣く彼女は、もはやただの普通の女の子に戻っている。
帰りのコンビニに同級生が

放課後、いつもの帰り道にあるコンビニへ寄った。涼しい冷気に迎えられ、何気なく雑誌コーナーをのぞくと――そこには同級生の姿があった。制服姿のまま、真剣な顔で漫画を立ち読みしている。ページをめくる指先は夢中そのもの。

だが、僕の心に芽生えるのは別の衝動だ。この世界では、誰に対しても僕の強制イラマチオは許される。彼女は泣きながら身をよじる。周囲の客たちはちらりと見るが、すぐに視線をそらす。ここでは、それが日常だからだ。
コンビニの美人店員

会計に並ぶと、レジにいたのは小柄で愛嬌のある女の子だった。制服の姿で「いらっしゃいませ」と微笑むその顔に、一瞬で目を奪われる。手際よくバーコードを読み取る仕草さえ可愛らしい。だが――僕の中で疼く衝動は抑えられなかった。

会計が終わる瞬間、僕は軽く身を乗り出し、彼女をひざまづかせた。客たちは一瞬こちらを見るが、誰も止めない。彼女は頬を赤らめながらも「ま、またどうぞ…」と笑顔を崩さず言葉を返す。袋を受け取った僕は満足げに店を出た。今日もま
帰りの公園に泥酔OL

家に帰る途中、ふと立ち寄った夜の公園。街灯の光がまばらに差し込み、虫の声が静けさを際立たせていた。そのベンチに、一人腰掛けている女性の姿があった。スーツ姿のOLらしく、缶チューハイを片手に、赤らんだ頬でため息をついている。「はぁ…仕事やめたい…」と誰にともなくつぶやく声は、夜気に溶けて消えていく。


僕はベンチの脇に立ち、そっとペニスを差し出す。彼女は「ひゃっ!?な、なにっ…、やめ…!」と叫び声をあげ、酔いで緩んだ表情がさらに崩れる。僕は彼女が酔っていることをいいことに、本番までさせてもらうことにした。夜風に喘ぎ声が響き、僕は満足げに公園を後にした。
こうして僕の一日は幕を閉じた。朝から夜まで、誰もが当たり前のように「イラマチオ」を受け入れる世界で、明日も僕は楽しむことだろう。