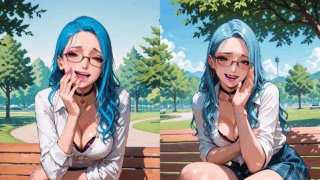僕はいつも通勤途中にある美人店員に好意を抱いていた(僕はでぶのおっさん)


僕の心の中では、いつもあの美人店員に好意を抱いていました。でも、彼女にはそんなそぶりは全くなく、ただの花屋のお客様としてしか認識されていませんでした。
そんなある日、彼女の裏垢と思われるアカウントを見つけた。


次の日の朝、僕は彼女近づいて携帯を見せた「これって君だよね?」
スマホ画面をそっと差し出すと、花瓶を拭いていた彼女の手がぴたりと止まった。息をのむ気配が伝わってくる。「……どうして……あなたがこれを?」細い声が震えている。

「偶然見つけちゃって。本当にご本人ですか?」沈黙が二人の間に落ちる。
「誰にも言わないって約束できますか?」
力強くうなずくと、彼女は観念したようにため息をついた。
「こっちへ来てください」そう言い残し、スタッフオンリーの扉へ向かう。
おぼつかない足取りで進むと、控室らしき狭い部屋の前で立ち止まり、鍵を取り出した。

ドアノブを握った彼女の指先は、微かに震えていた。
振り返った彼女は真剣な眼差しで言った。
「これから私が言うことは全部秘密です。いいですね?」ゴクリと喉が鳴る音さえ聞こえた気がした。
彼女が部屋に入り照明をつけようとする。その瞬間――ガチャリ。後ろ手に扉が施錠される音が響いた。


「このことを知っているのはあなただけです。だから……特別ですよ?」その言葉と共に距離が一気に詰められる。
次の瞬間には、柔らかい体と甘い香りに包まれていた。耳元で囁かれる声に理性が揺らぎ始める。
その姿勢のまま、右手が腰へと伸びていく。衣擦れの音がわずかに響く。そして――ジッパーを引き下げる独特の乾いた音がした。