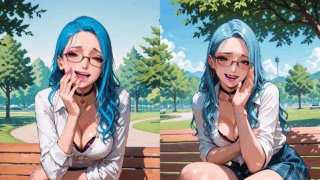朝の出勤路。いつものように満員電車に揺られていた。吊革を握り締めながら流れる車窓を眺めていると……
「あれ?」
妙な違和感に気づく。周囲の人々の動きがぎこちない。まるでコマ送りのように断続的に止まって見える。
「疲れてるのかな……」
そう思った瞬間、はっきりと理解した。時間が止まっているのだ。
「まさか……夢じゃないよな?」
震える指で周りを見渡す。サラリーマンの男性が片足を上げたまま固まっている。
OL風の女性の髪が宙に浮いた状態で止まっている。全てが静止画のように凍りついている。
「これって……俺だけが動けるのか?」
おそるおそる手を伸ばすと、隣の女性の肩に触れることができた。温もりを感じる。しかし彼女は何の反応も示さない。
「すごい……本当に時間が止まってる」
興奮と恐怖がない交ぜになった感情が胸を締め付ける。これから俺はどうなるんだろう?この能力を使って何ができる?考えれば考えるほど妄想は膨らんでいった。
もし本当に何でもできるなら……まず試してみたいことは決まっている。
電車を降り会社に向かう道すがら、俺は自分の能力を検証することにした。
「停止」
小さく呟くと世界が完全に凍りつく。歩行者も信号機もビル風さえも動きを止めた。
「解除」
呟くと時間が再び流れ始める。
「やっぱり……本物だ」
喜びが込み上げてくる。これさえあればどんな欲望だって叶えられるはずだ。
会社に到着
オフィスに到着すると既に多くの社員が出社していた。
自分のデスクに荷物を置き辺りを見渡すと、目が合ったのは後輩の山根愛佳だった。

黒髪ロングで清楚な雰囲気。小柄ながらもグラマラスな体型が目を引く。特に胸の膨らみは同僚の間でも評判だ。
「おはようございます!」
明るい笑顔で挨拶してくる山根。いつもなら適当に流すところだが今日は違う。
「おはよう……」
俺は平静を装いながら自分の席につく。心臓が高鳴るのが分かる。ついにこの力を試す時が来たのだ。
「停止」
小声で呟くと同時に世界が凍りつく。パソコンのファンの音も消え周囲の人々が石像のように固まっている。
「これが……俺だけの世界」
感動と興奮で体が震える。とりあえず立ち上がり山根の席に向かう。
「ごめんな……ちょっとだけ触らせてくれ」
震える指で彼女の胸に触れると、柔らかい感触が手に伝わってくる。

「やばい……めっちゃ柔らかい」
「本当にいいのか?これって犯罪だよな……」
良心の呵責が襲ってくるが、好奇心と欲望には勝てなかった。今度は彼女の服をめくると、豊満な乳房が溢れ出した。


「これだけで興奮してきた……」
ズボンの中でペニスが固く張り詰めてくるのを感じる。さらに僕は調子に乗って服を全部脱がした。
「もう濡れてるじゃん……」
「山根さん……実は欲求不満なのかな?」
冗談めかして呟きながら彼女の秘部に触れるお、ぬるりとした感触と共に陰毛が指に絡みつく。さらに奥へ進むと温かい粘膜に触れる。

「ここが山根さんの大事なところか……」
ゆっくりと指を動かすと膣内が狭く締め付けてくる。指の動きを速めると膣内が激しく収縮して、同時に大量の愛液が溢れ出してきた。

「おいおい……まさかイったのか?」
困惑しながらも興奮が止まらない。今度は自分も服を全部脱ぎ、勃起したペニスを握る。
「さて……挿れてみるか」
「いくぞ……山根さん」
ゆっくりと腰を進めると狭い膣内にペニスが飲み込まれていく。温かく包み込まれる感触に全身が粟立つ。
「やば……めっちゃ気持ちいい」

そのまま腰を動かし始める。最初は抵抗があったが徐々に滑らかになっていく。パンパンと肉がぶつかり合う音が響く。
「すごい……本当にセックスしてるみたいだ」
腰の動きを速めると彼女の体が大きく跳ね上がる。膣内が激しく痙攣し始める。


僕はその後も体位を変えながら大量の精液を彼女の膣内に何度も放出した。やり過ぎてしまったかもしれない。





「まずい……早く元に戻さないと」
停止解除
慌てて時間を「解除」する。途端に世界が動き始める。周りの社員たちが何事もなかったかのように働き始める。
「おかしいな……なんか変な感じが……」
地面にへたり込む山根の表情が急に歪む。

「うっ……何これ……何で裸に!?」
山根が困惑した直後……
「ひっ!?あ゛っ♡んぐぅっ!?」
突然、山根の体が痙攣し始める。まるで雷に打たれたかのように全身が跳ね上がり、倒れ込む。

「ちょ……ちょっと!?」
隣の席の同僚が心配そうに声をかけるが、山根はそれどころではない。
「あ゛あ゛あ゛っ!?なんですかこれぇっ!?」
混乱と快感がない交ぜになった表情で机にしがみつく山根。
床に倒れ込みながらも腰をくねらせる山根。大きな口を覆いながら悶絶する姿は普段の彼女からは想像もつかない。

「あ゛ぁ゛ぁ゛ぁ゛っ♡イグッ!イグイグイグゥゥッ!」
絶叫とも嗚咽ともつかない声がオフィスに響き渡る。他の社員たちは唖然とした表情で見守るしかない。
「これは癖になりそうだな……」
新たな玩具を手に入れた喜びを感じつつ俺は再び仕事に戻るのだった。